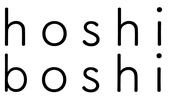140字小説コンテスト
季節の星々(冬)

冬の文字
重
作中に「重」という文字を入れる
募集期間
2025年1月1日〜31日
応募総数
1004編
選考
ほしおさなえ
星々運営スタッフ
選評
ほしおさなえ
2020年7月からはじまった星々の140字小説コンテスト。5年目を迎える今年、大きな改革をおこなうことになりました。これまで星々の運営とほしおで選考をおこなってきましたが、外部の方を招いて選考委員会を設置します。
これまでのコンテストの優秀作を見るうちに、俳句や短歌が文学であるのと同様に140字小説も文学になり得ると考えるようになりました。もちろん、書けばなんでも文学になるとは思っていません。俳句や短歌が文学になったのもそうなるように育ててきた先人がいるからです。育てるためには作品を厳しく見る目、良いものを見出す目も必要です。そして、ひとりではなく、複数の人で育てていくものだと思うのです。
単にいろいろな人が集まればいいわけではなく、広がりを持ちながら、共通する志を持った人たちが集い、育てていく。これまでのコンテストで、自分とは違う、しかし自分と共通する志を持つと感じる優秀な書き手と出会いました。その方たちに選考を委ねることが、さらに広がりのある場を作ることにつながると考えています。2025年度からは、各回の選考は選考委員会が行います。そして、選考委員会が選んだ作品の中から、わたしが年間グランプリを選びます。
わたしが各回の選評を書くのは最後になりますので、140字小説を書く上でのポイントをひとつお伝えしておこうと思います。短い形式ですから、着眼点が重要です。大切なのは、いつもとは違うレンズを通して世界を見るということです。いつもより細かいところまで見えるレンズ。遠くまで見えるレンズ。ゆっくりに見えるレンズ。別の形に見えるレンズ。時を超えるレンズ。自分なりのレンズを見つけて世界を見つめてください。
入選。佐伯功一郎さんの作品。鯨がこれまでどのような生を送り、終えていこうとしているのか、くわしいことは描かれていません。しかし、これまでに長い時間があったことがわかります。画家は鯨と対峙します。世界そのものと向き合うかのように。世界に対して人ができることはわずかしかありません。それを受け入れ、自分を見る鯨の目を描く。覚悟の物語だと感じました。祥寺真帆さんの作品。会社役員のある瞬間をとらえた軽いタッチの作品ですが、そこに込められたものには思いがけないほどの重さがあります。みな若いときにはそんな日が来るとは思っていない。喜び、楽しみ、苦しみ、もがきながら日々を送り、あるときふとそうした日々がすべて過去になっていることに気づくのです。歳月が凝縮された、まさに文鎮のような作品でした。空見しおさんの作品。雪のあとにやってくる怪獣。子どもの目から見た世界が生き生きと描かれています。「押しのけながら」「歩きながら」というリズムが心地よく、高鳴る「ぼく」の気持ちが伝わってきます。映像的な表現が魅力的な作品でした。
佳作。羊の耳さんの作品。女の子の心に空いた穴。しかし、穴が空いたことで心臓は外の世界を知ります。女の子の気持ちではなく、胸のなかにある「心臓」に目を向けたところが新鮮です。藤沢恵さんの作品。人々の言葉が葉っぱのように落ちていて、毛虫たちが集めていく。その発想が素敵です。公園の生活者を温められる葉だけを選ぶのはきっと大変なことでしょう。灯籠が祈りのようです。月越瑠璃さんの作品。ほっと心が温かくなる、お正月の風景が描かれています。言葉を交わすことで、意味以外のものが伝わっているのがわかります。見坂卓郎さんの作品。父の脱皮を描いた不思議な味わいのある作品です。タイミング、処理方法など脱皮のディテールが素晴らしく、いくら脱いでも体重が落ちないところがなんとも切ないです。石原三日月さんの作品。大事な仕事を控え、人も時計も眠れない、そんな夜。時計といっしょに海辺にドライブに行くという展開が素敵です。酒部朔さんの作品。ピアノ教室での風景。厳しいレッスンのあと、ココアを飲みながら静かに雪の音を聞く。短いなかに描き出された緊張と緩和の対比が見事です。ケムニマキコさんの作品。いまの風景のなかに、もうここにないものを重ねる。長く生きているとそういう瞬間が増えてくる気がします。この世界はもうここにないものが積み重なってできているのかもしれません。
四葩ナヲコ(星々運営)
わたしが140字小説に出会って、そろそろ10年になります。そのうちの半分近い期間、「月々の星々」「季節の星々」の担当として毎回たくさんの作品を読み続けてきましたが、全く飽きないのが不思議です。毎回毎回面白い。小説は(それが事実を元にしたものでも)ある意味すべて絵空事ですが、この140字に凝縮された絵空事に、まごうかたなき真実が宿っているのを、いつもありありと感じます。書き手の皆さまがそれぞれに掴んだ真実を、この140字にのせて届けてくれている。そう思って大切に読んでいます。
佐伯功一郎さんの作品は、浜辺に打ち上げられた鯨と、それを見つめる画家のひとときの交感を描いています。身体を動かす力のない鯨の最期のときを「闘い」と呼んだのは、死に対して懸命に抗う意志が間違いなく鯨にあったから、それが画家には伝わったからなのだと感じました。祈りをやめて絵を描きはじめる画家もまた、自分自身の闘いを選んだのでしょう。それをさらに物語の外側で見つめるわたしたちにも、生きること、闘うことの覚悟を問うているような物語だと感じました。
祥寺真帆さんの作品は、重鎮と文鎮を重ね合わせた言葉遊びが面白く、比喩として鮮やかに展開していく様子が巧みでした。重鎮と文鎮、どちらも「おもし」で、人や物を押さえつける存在ですが、ここで語られる物語は不思議に軽やかです。特に、若手の活躍を「とめ、はね、はらい」と書道の筆遣いになぞらえたくだりは、なんとものびやかな心地がして、読んでいるわたしも心が軽くなりました。煙たがられながらも陰で若手を支える重鎮が、口ではぼやきつつもその立場を愛していることが伝わってきます。
空見しおさんの作品は、子どもの目から見た世界。雪が積もることそれ自体も、かき分けられた雪の塊も、大人にとっては厄介な面倒ごとですが、子どもにとってはわくわくする想像のピースです。こんなふうに季節を、世界を丸ごと楽しんでいたころが自分にもあったと懐かしく、また羨ましく心を揺さぶられました。「カーテンの隙間から覗く」という怪獣との距離感も絶妙です。安全な場所で安心できる人々に守られているからこそ、自由に想像を広げていくことができるのだろうと感じ、あたたかな気持ちになりました。
佳作では、羊の耳さん、見坂卓郎さん、ケムニマキコさんの作品が印象的でした。穴の開いた心から初めて外の世界を見た心臓、脱皮を繰り返す父親、どこにもなくなってしまった風景、どれも書き手が自分だけの感覚でとらえた真実が、まっすぐに書き記されていると感じました。
入選
佐伯功一郎
夜の浜辺で一匹の鯨が死にかけていた。鯨は砂の上で飛び跳ねれば生まれ育った海に帰れると思ったが、その重い身体を動かすだけの力は残ってはいなかった。一人の画家だけがその鯨の最期の闘いを見守っていた。画家は途中から祈ることを止め、画具とランタンを取りに帰ると、自分を見る鯨の目を描いた。
祥寺真帆
重鎮と呼ばれている。「というか文鎮か」役員室の椅子にずっしり腰を下ろす。尊敬ではない、それどころか煙たがられている。けれどもまあ、そういう役回りが来たのだ。君らが自由に筆を持ち、とめ、はね、はらい、よそから風が吹けば飛ばされないようにしているんだがな、と戦略資料のファイルを開く。
空見しお
雪が降り続いたあとの夜は、低く重たい唸り声とともに怪獣がやってくる。道路に積もった雪を左右に押しのけながら、ゆったりと歩きながら、カーテンの隙間から覗くぼくに気付くと、大きな指を小さく振ってくれる。朝になると、家の前に転がる雪の塊を見てママが溜息をつくけれど、ぼくは怪獣が好きだ。
佳作
羊の耳
心にぽっかり穴を空けた女の子が、重い足取りで夜道を歩く。胸の心臓が透けて見えた。心臓は穴が空いて初めて、穴を通して外の世界を見た。何もかもが新鮮。「お日様を一目見れたら、すてきだな」心臓が言った。女の子は星の匂いの残る風を力強く吸い込む。穴が空気で膨らむ。まだ塞がらないでと祈る。
藤沢恵
ベンチの下に住む毛虫は冬になると人々の落とした言の葉を集める。「ありがとう」はしっとり紅く「さようなら」はずっしり蒼い。集めた言葉で虫は毛布を編み、公園の生活者にかけてまわる。ああ、これで寒さを凌げると毛布は評判で、重ね掛けするといっそう光は増し、夜は雪を照らす灯籠になるという。
月越瑠璃
90代の祖父はきつい東北訛りで、時折言葉が聞き取れない。最近は加齢も手伝い、さらに不明瞭になった。3才になったばかりの子は、「ひいおじいちゃん!」と駆け寄った。こちらも喋りは今一つ。それにも関わらず、ふたりはゴキゲンだ。噛み合わない会話も、互いを見つめ話すだけで重なってゆく正月。
見坂卓郎
重たい服を脱ぐように、よっこらせという感じで父は脱皮する。タイミングはまちまちで、二日続くこともあれば一か月空くこともある。残業後に脱皮することが多いので、たぶん会社であった嫌なことを脱ぎ捨てているのだろう。皮は燃えるゴミになる。いくら脱いでも父の体重が落ちる気配はない。
石原三日月
夜中に肩を叩かれて振り向くと、目覚まし時計だった。早朝から大事な仕事があるので、何度も確認して時間をセットしたのだが。「責任が重すぎて寝つけません」。そうか奇遇だね、じつは僕もだよ。助手席に時計を乗せ、ドライブへ出掛けた。いま海沿いのSAで珈琲を飲みながら、一緒に朝を待っている。
酒部朔日(酒部朔より改名)
家にある練習用の電子ピアノは鍵盤が軽すぎて、ピアノ教室の重い鍵盤をうまく弾けない。先生は強く蓋を閉めて何度も怒る。でも今日は雪の日だ。雪の日はココアの日だ。私は赤く沁みる瞼にココアの湯気を浴びる。無言で先生と屋根の雪が落ちる音を聞く。こんな時に音楽をかけない先生を好きだなと思う。
ケムニマキコ
線路沿いに田圃が広がっていてね、そこを歩いて帰るのが好きだった。重たそうな稲穂が風にさざめいて、金色の海になるのが好きだった。それはもうどこにもない。けれど確かにここにあった。人影のない駐車場で、私は夕暮れに佇む稲穂になる。目を閉じて風を待つ。祈るように俯いて、あの日の風を待つ。
2024年度下半期「季節の星々」受賞作は、予選通過作とあわせて雑誌「星々vol.7」に掲載します。
サイトでは2025年6月30日までの期間限定公開となります。
下記のnoteで応募された全作品を読むことができます。
この記事をシェア