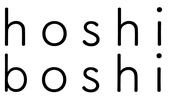140字小説コンテスト
季節の星々(秋)

秋の文字
深
作中に「深」という文字を入れる
募集期間
2023年10月1日〜31日
応募総数
569編
選考
ほしおさなえ
星々運営スタッフ
選評
ほしおさなえ
140字小説にはさまざまなジャンルの作品があります。身近な日常を描いたもの、ファンタジーやミステリ、SF、ホラー風味のあるもの。読ませどころもいろいろです。オチでうなるもの、クスッと笑えるもの、強い思いに心揺さぶられるもの。出版されて話題を呼ぶ作品もあり、書き手の裾野が広がってきていることも感じます。そうしたなかで、星々の140字小説コンテストでは、星々ならではの作品を選ぶように心がけています。ジャンルは問わない、ただしきれいにまとまって終わりではなく、その向こうが見える作品、「簡単に言葉にできないこと」と自分なりに向き合っている作品です。ほんとうは作品に順位をつけるのはおかしなことなのですが、こうした複雑な味わいの作品には、その良さをしっかりと紹介する場所が必要です。こうした作品を世に送り出すことが星々の大事な使命であると考えています。
一席の石森みさおさんの作品。世界を壊すほどの寒さに包まれた世界。人が外に出ないため、争いのない静かな日々が続く。作者が意識したかはわかりませんが、コロナ禍を思わせるような状況です。しかしその状況が遠のき、いまは世界のあちこちで厳しい争いが起こっています。いまの世界に生きるわたしたち全員にとって他人事ではなく、この作品からはその切実さが伝わってきます。争いはいつも自分の大事なものを守るために起こります。武器を持つか持たないかは命のかかった重い選択です。そのような状況がいつ訪れるのかはだれにもわからず、訪れたときにはだれでも瞬時に決断を下さなければならなくなる。決断しないまま物語は終わり、だからこそその重さが読む人の胸に深く残ります。140字でこのテーマを扱い、実感を伴う作品に仕上げられたことに驚き、ぜひ一席に、と感じた作品です。二席のケムニマキコさんの作品は、体温が匂い立つような、別の重さを持った作品でした。ここに描かれるふたりの背景には、逃げることのできない辛い現実があるのでしょう。語り手はその現実を前に、怒るのでもなく、呪うのでもなく、ただ相手を守り、ともに生きようとします。なりふりかまわないその強さ。命の息吹がなまなましく迫り、読み手を圧倒します。三席の想田翠さんの作品にはあたたかな日常が描かれています。かつて母に作ってもらった夜食。いまは自分が親になり、子どものために夜食を作っている。記憶がよみがえり、自分の気持ちがそのときの母の気持ちに重なっていく。ひとりの人間が成長し、子どもを育て、そして老いていく。その営みのあたたかさが浮かび上がる、宝物のような作品でした。
佳作。富士川三希さんの作品。ひとり静かに歩く語り手。なにかを失っても、記憶は残る。そうして、命ある限り生きていく。「ほてほて」というやわらかな足音に、小さくも強い命の力を感じます。リツさんの作品。大きな悲しみに見舞われ、好きだったいちご大福の味も感じない。その味とともに、かつて存在した大事な時間まで失われてしまったように感じたのかもしれません。書き手にとっていかにその時間が大切だったのかが伝わってきます。坂本真下さんの作品。語り手はかつて人魚だったけれど、いまは人間。深海行きのバスに乗っている。人魚に戻りたいわけではない、または戻れないのかもしれません。その語り手にそっと会いにくる兄。水の世界の雰囲気が印象的な作品です。はぼちゆりさんの作品。扉を開けるともうひとりの自分がいたという不思議な物語。繰り返しの構造も魅力的ですが、自分自身とじっくり話すという発想に新しさを感じました。ふとこぼす「私の方が消えればよかったのに」という呟きにリアルな感触がありました。鈴木林さんの作品。深夜のファミレスに集まる家族。それぞれ個性的で、理解しあっているふうでもありませんが、ファミレスで過ごす姿が楽しげで、家族とはこういうものかもしれない、と思わせます。瓦夜さんの作品。涸れ井戸の底にいる語り手。上にいる人々の目から涙が落ちてくる。これが溜まれば浮かんで外に出られるかもしれない。諦めつつも現状を笑い飛ばすような「千年後くらいには、恐らく」という言葉が秀逸です。あきらさんの作品。この前まで生きていたものがすっかり空っぽの死体になっている。中にあったはずの命は消えてしまった。あったものがなくなることに対する恐れが鮮やかに描き出されています。
四葩ナヲコ(星々運営)
書き手のひとりとして140字小説と向き合うとき、限られた文字数に入りきらなかったことは切り捨てるしかないという点に、わたしはいつも難しさと面白さを感じます。だからこそいっそう、なのかもしれませんが、読者として140字小説を楽しむ際には、書かれているものが全てではない、140字で切り取った時間と空間の外側に、まだ世界が続いていることを感じさせる作品に強く心を惹かれます。
一席、石森みさおさんの作品。語り手の「僕」は猫を抱き、微睡み、ふるえるのみではっきりした行動を起こしません。雪に埋もれた世界は静かで、まるで時間が止まってしまったようです。しかし、このひとときには過去と未来があります。寒さがやってくる前(過去)にあったとされる争いからは、我々の現実の世界で起きている争いがいやおうなく思い起こされ、(現実世界では各地で今も続いている)争いが寒さで消えてしまったという部分からは、人々の関心がいっとき盛り上がって消えてしまうことを連想しました。そして、猫の餌が尽きたら自分が武器を持つという可能性(未来)。猫のぬくもりは希望であっても、それを守るためには争いに足を踏み入れることになります。争いそのものの大義と、個人が争いに加わる動機には落差があるのだとつきつけられたように感じ、はっとさせられました。
二席、ケムニマキコさんの作品では、深泥池という実在の池とその特異な生態系を、少女たちの境遇にリンクさせる仕掛けが巧みでした。彼女たちが抱える困難は作中で詳しく語られることはないのですが、「ズタズタにされた上履き」にその一端を垣間見ることができます。ラストの「キンモクセイの匂いは夕方みたいや」という一文、夕方みたいだと感じた夕方ではない時間、二人はやわらかな光の中に駆け出したのだと、わたしは想像しました。実際には自分たちでは解決できない困難がそこにあったとしても、一緒に行こうと言ってくれた人がいたことがこの先きっと力になる、その思い出が薄暗くないこと、キンモクセイの匂いに包まれていることに希望を感じました。
三席、想田翠さんの作品は、夜食の思い出から始まり、今は語り手自身が夜食を作る側になったことがわかる温かい話。慌てて漫画を隠すというエピソードがリアルです。「勉強熱心な子どもとそれを応援する親」というステレオタイプの美談ではなく、ありのままの親子の日常であることに親近感を持ちました。わたしが特にいいと思ったのは「味方だよ」のひと言。「受験がんばれ」や「勉強がんばれ」ではなく、「味方だよ」というエールから、普段の親子関係も目に浮かぶようです。自分の母親から送られ続けていたものをしっかり受け取って、それを我が子にまた渡していくという大きな時間の流れと、日々のささやかなひとコマを同時に描いた素晴らしい作品でした。
佳作では、富士川三希さん、坂本真下さん、あきらさんの作品が特に印象に残りました。なくしてきたものたちの間を歩いてきたという実感、何やらいきさつがありそうな人魚の兄弟の再会、幼子が季節の移ろいの恐ろしさに気づいてしまった瞬間。どの作品も、文章の中に書かれていることだけではない物語の広がりや奥ゆきが感じられるのが魅力的でした。
入選
一席
石森みさお
熱波から一転、厳しい寒さがやってきて、街は文明を壊す程の深い雪に埋もれてしまった。世界の半分がそんな様子で、寒い代わりに争いの火は消え、みんな静かに身を寄せ合っている。僕は懐に猫と空腹を抱いて束の間のぬくみに微睡むけれど、この子の餌が尽きたら僕も武器を持つのかな、とふるえている。
二席
ケムニマキコ
サイトからの投稿
深泥池の浮島はな、植物の遺体が積もってできてるんやって。ほんでな、そこに根を張って、新しい草木が生えるねん。私らも、そんな風にしよな。私が一つの島になって、あんたの居場所になったげる。ズタズタにされた上履きを放り投げ、私達は駆け出した。キンモクセイの匂いは、夕方みたいやと思った。
三席
想田翠
深夜まで勉強していると、母が夜食を作ってくれた。基本的に温かいうどんかおにぎりで、たまに登場する焼うどんの特別感ったら…。踊る鰹節が回想を連れてきた。階段を上がる足音を聞いて、今頃慌てて漫画を隠しているはず。経験者だからわかる。それでも、「味方だよ」のエールを送る心は変わらない。
佳作
富士川三希
少し角が丸い風を深く吸いこむと、肺に透き通った朝が流れこみ波立つ稲の薫りが鼻をかすめる。あの地はアスファルトの下へ消え、あの人は空の上。そのあいだを随分歩いてきたものだ。思い出すたびに胸が締めつけられても一生手放すことのない記憶が、今日も私の足を前へ進める。ほてほてと生きるのだ。
リツ
深夜に食べたいちご大福は味がしなかった。いつもは夕食の後にお茶を飲みながら味わって食べるいちご大福を、今日は作業として食べた。長すぎる夜の過ごし方が分からなくて食べた。気を紛らわすために食べた。鼓動を落ち着かせるために食べた。美味しくて幸せな思い出に上書きされて、悲しくて泣いた。
坂本真下
サイトからの投稿
深海行きのバスに俺は飛び乗った。跳ねる息を落ち着かせながら席に座る。もう何年も使っている肺なのに、まだ呼吸は慣れないらしい。砂浜を出発したバスは底へ向かって走り、光が車内灯だけになって暫く一匹の人魚が窓を叩いた。遠い昔俺が捨てた尾鰭を持ったままの兄が手を振っている。会いに来たよ。
はぼちゆり
ガチャリと家のドアを開けると、私がいた。話してみると、とても趣味が合い、時間を忘れて語り明かした。目覚めるともう夕方で、もう一人の私はいなくなっていた。呑んだ後始末をしながら「私の方が消えればよかったのに」と深い溜息を吐いた。もうすぐ日が暮れる。ガチャリと家のドアが開いた。
鈴木林
深夜営業のみのファミレスには家族が集まった。一人暮らしの父、ひとつところにいない母、身長2メートルの娘、煙草を食べる息子、漢字を編み出す犬。フライドポテトを掛け金にしてトランプで遊ぶ。朝になるとドリンクバーが調子を崩し薄い炭酸を吐き出すので、皆はしぶしぶ個別会計しそれぞれ帰った。
瓦夜
深い涸れ井戸の底に私は居る。光を求め見上げると、丸い空は人々の顔で埋まっている。彼らの唇は絶えず動き、様々な意見が交わされている。話し合いが終わると、彼らの瞳から、雫がぽつぽつ落ちてくる。その涙で涸れ井戸に水が溜まり、私は地上へと浮上する。これで助かる。千年後くらいには、恐らく。
あきら
砂利の上に、死んだオニヤンマがおちている。夏の間空を抱いていた羽は深く透きとおり、アキアカネが秋空を無数に泳いでいくのを、大きな眼で睨みつけている。あれだけきらめいていた夏が、呆気なく空っぽになりそこにおちていた。鮮やかな秋に責め立てられ、わたしは恐ろしくて、母の手を握る。
第4期下半期「季節の星々」受賞作は、予選通過作とあわせて雑誌「星々vol.5」に掲載します。
サイトでは2024年6月30日までの期間限定公開となります。
下記のnoteで応募された全作品を読むことができます。
この記事をシェア